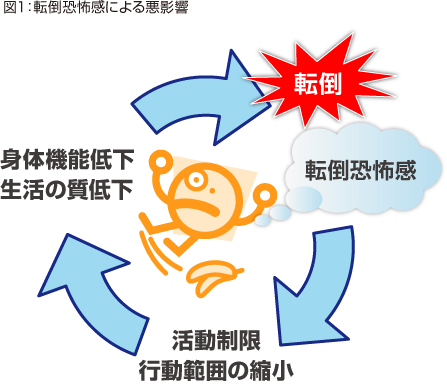文献レビュー
NEW!
(204)DTを使用したTUGにおいて、認知タスクと運動タスクに違いがある?
February 08, 2020
【一言メモ】
この論文では、地域在住高齢者にとって、認知デュアルタスク(計算)を使用したTUG(TUGcog)は転倒のリスク増加を特定するための有効な評価であることを示しています。なおかつ、TUGcogのカットオフ時間として10.0秒を推奨しています。通常のTUGと運動デュアルタスク(水の入ったコップを持つ)のTUG(TUGman)では、転倒リスクを高く評価はできなかったとしています。地域在住高齢者にとっては、TUG・TUGmanは容易すぎるため、認知タスクを使用することが有効なのかもしれません。
(163)肩に痛みを持つ者はバランスが悪くなる!?
February 02, 2019
【一言メモ】4ヶ月以上肩に痛みを持つ30代から80代を対象にバランスや姿勢安定性を調べたところ、健常者と比較し、バランスや姿勢安定性が低下していたとしています。今後、バランストレーニングにより肩機能の改善につながるかということを述べていますが、3月の愛知県PT学会では、肩機能の改善がバランス機能と関連した症例について発表します。
(112)アルツハイマー病患者に対するVASを使用した痛み評価
October 31, 2017
認知症の痛み研究を盛んに行っているScherder先生の論文です。既存の痛みの評価である視覚アナログスケールは、アルツハイマー病患者の場合、健常高齢者と比較して小さく示してしまうようです。やはり痛み行動評価を併用する必要がありそうです。
(98)高齢者の運動学習における神経適応の仕方は若年者と異なる!?
August 14, 2017
出力調整課題の練習において、若年者は動筋と拮抗筋の両方で調整し適応していたが、高齢者では動筋のみを調整し適応させていたことが示されました。私が以前に行った歩行速度のグレーディング研究でも、若年者は空間、時間パラメータの両方で調整し、高齢者は空間パラメータのみで調整していることが明らかになっています。高齢者はより簡単な方法で課題に適応するようですね。>>>歩行速度のグレーディング研究